今年も9月になりました。2024年度調剤報酬改定が施行されて早くも3か月。
その影響は例年よりも大きいように感じます。
特に施設基準である地域支援体制加算の算定要件が大きく変わり、幅広い活動が評価される形となりました。
それにより、あまり今まで話題に上がっていなかった外来服薬支援料1の算定需要も増え、名前を聞くことも多くなったように思います。

今まで地域支援体制加算を算定していた店舗でも、この項目は捨てていたところが多いのではないでしょうか。
そんな中で、こういった疑問が沸いている方も多いのではないでしょうか。
- 算定したいと思っているが、誰が対象でどういうアプローチをすればいいかわからない
- どういった流れで算定できるかわからない
- 注1と注2があるけど、それらの違いがよくわからない
- そもそもなにをすれば算定できる調剤報酬なのかもよくわからない
実際、外来副支援料1はかなりややこしい算定要件をしているかと思います。
今まで一度も算定経験がなく、自分の所属店舗にとってはそもそも無縁だと思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、実は全くそんなことはありません。
今までそこら中に転がっていた算定のチャンスを、見逃していただけの可能性もあります。
本記事を読めば
- 外来服薬支援1の概要
- どういう場面で、どういう患者さんに対して算定できるか
- 算定タイミングや全体の流れ、必要な書類の書き方
を理解することができます。
そして、あなたも2か月以内に1件以上を算定することが可能です!
この記事を書いている私は、薬剤師歴18年。某薬局グループでエリアマネージャーをしております。
5月からの3か月で担当12店舗全てにおいて2件以上の外来服薬支援料の算定を果たすことができました。
多いところでは月に6件以上のペースで算定できております。
本記事では、その過程で得たノウハウを皆さんに紹介していきたいと思います。
外来服薬支援料1の算定要件
まずはこのおさらいから始めましょう。
本算定は注1と注2にわかれており、それぞれ細かい要件が異なりますが、大まかに説明をするならば、
注1
- 一包化されていないor複数の科で別に一包化されている現在服用中の薬剤について、まとめて一包化をしたり服薬カレンダーを活用して整理
- 処方医の許可が必要
- 結果として他の保険薬局でのみ調剤された薬剤のみについての服薬支援でも算定可



注1では一包化をすることが多いかと思います。その場合、基本的には外来服薬支援料2の要件を満たす必要があることに注意です。
注2
- 患者もしくはその家族が持参した残薬を整理(一包化含む)
- あらかじめブラウンバッグ運動※の取り組みが必要
※ブラウンバッグ運動とは:患者さんに対して保険薬局に服用中の薬剤等を持参する動機を作るために無料でバッグを提供し、服薬管理を行う取り組みのこと - 処方医へ情報提供(事後報告可)が必要
より詳細な算定要件を知りたい方は下記関連ページをご覧ください。
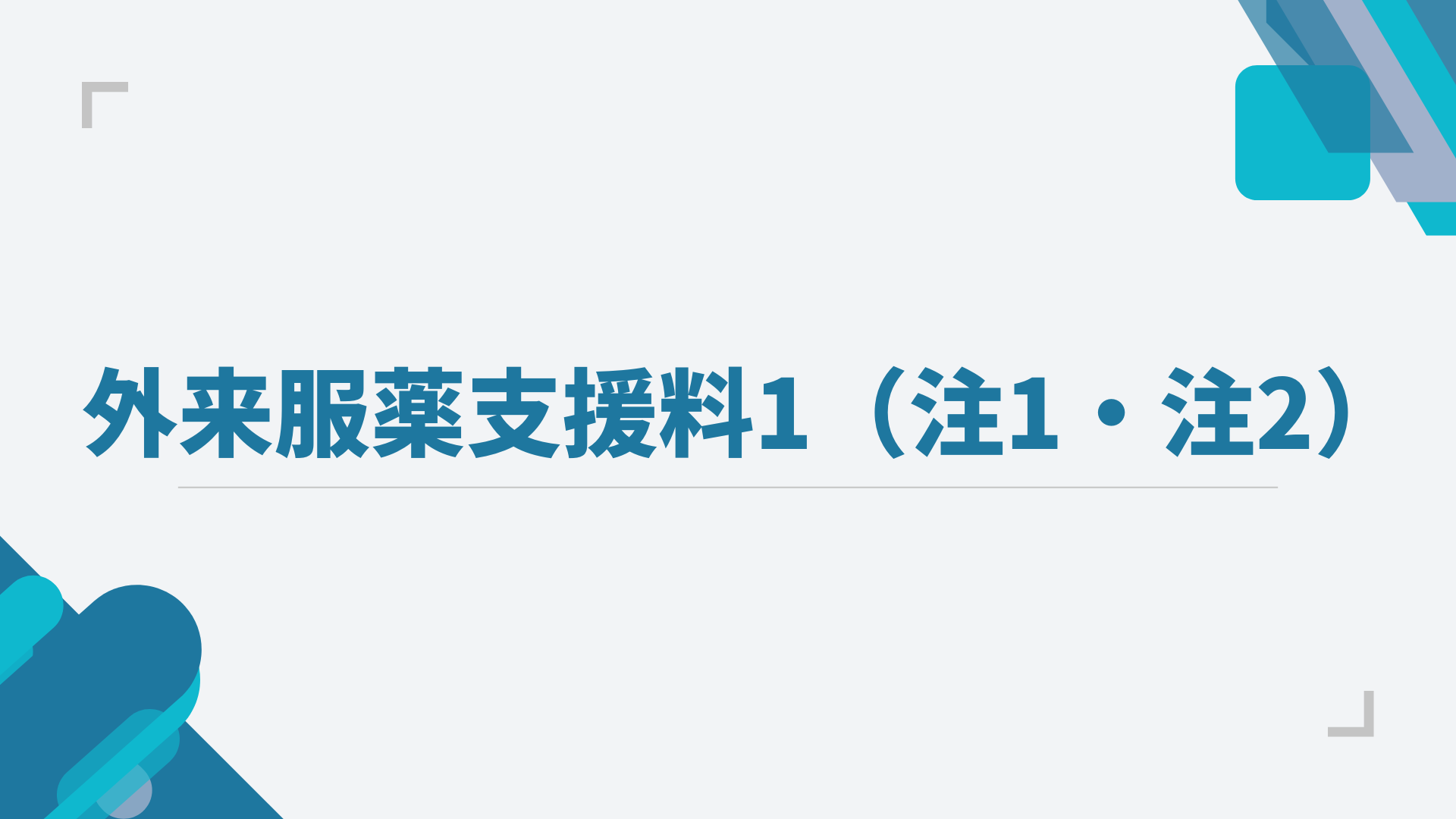
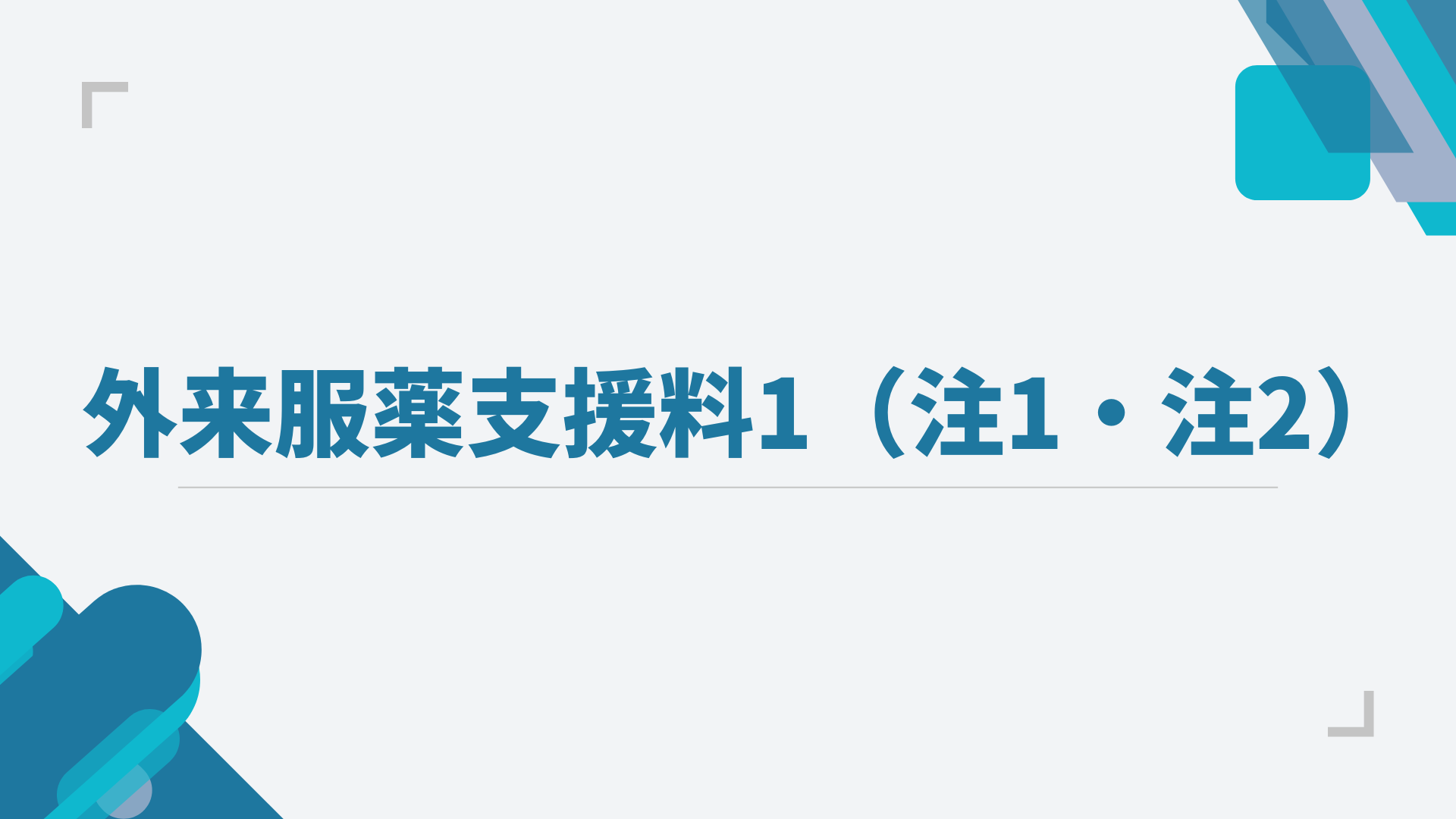
注1と注2の違いについて
外来服薬支援料1については、その中で注1と注2の二種類に分かれております。



実際にすでに算定している方でも、どちらで算定するべきなのかよくわからないと感じたことは多いのではないでしょうか?
こちらも外来服薬支援料1がなんとなく敬遠される所以の一つかと考えられます。
先に結論を申し上げれば、要件を満たすならばどちらで算定をしてもかまわないでしょう。
とはいえそれぞれの要件の違いもいまいちわからないという方も多いかと思います。
この二つの違いについて、私個人の意見も交えながら解説をしていきます。
まずは、以下の表をご覧ください。
| 注1 | 注2 | |
| 患者・家族等または医療機関の求めに応じて実施 | 〇 | 〇 |
| 患者・家族等が薬局に薬剤を持参 (あらかじめ薬剤師を入れる袋等を提供し、ブラウンバッグ運動を周知) | 明記なし (すなわち、薬剤師が患家を訪問した場合でも可) | 〇 |
| 当該薬局以外で投与された薬剤を確認(重複投薬・相互作用の確認、処方医への照会等を含む) | 〇 | 明記なし |
| 服薬支援の対象薬剤 ①当該薬局で調剤した薬剤のみ ②他の薬局で調剤した薬剤のみ ③院内投薬された薬剤のみ | いずれも算定可 | いずれも算定可 |
| 処方医に当該薬剤に治療上・服薬管理支援の必要性を確認 | 〇 | - |
| 服薬支援・管理の結果を医療機関へ情報提供 | - | 〇 |
この表から、ある程度は明記されていますが、グレーゾーンも多いことがわかります。
おそらくケースによっては、どちらで算定することも可能なもの多々あり得るかと思われます。
ポイントとしては、
- 患者・家族等が薬局に薬剤を持参したのか(両方該当)、訪問して回収をしたのか(注1)
- 処方医に事前に必要性の確認を行ったのか(注1)、事後に情報提供を行ったのか(注2)
- 一包化をしたのか(両方該当)、残薬の整理のみを行ったのか(注2)
- ブラウンバッグ運動を行っていない(注1)
ただし、これらはor形式で書きましたが、両立することもあり得る内容です。
結局どちらで算定するかはケースバイケースで、その時最も自然な流れで算定しやすい方を取りに行けば良いのではないかと思います。
以上のポイントを押さえ、次は算定対象を探してみましょう。
算定対象の見つけ方
本算定は、その名の通り、服薬支援が必要な外来患者さんが対象となります。



とてもわかりやすいネーミングですね。
つまり、薬局に訪れる患者さんの中で、
- ポリファーマシー
- 日常的にアドヒアランスが不良
- 普段より一包化している
- 認知症が進んできている
- 家族orヘルパーさんが薬を取りに来ている
こういった特徴をもつ方々です。
少し目をつぶって考えてみましょう。
普段業務をしている中で、そういった患者さんに出会うことは、決して少なくないのではないでしょうか?
今何人か思い浮かんだならば、きっとその10倍は実際に来客されているはずです。
普段より意識して応対することで、対象患者さんを発見することができます。 これがまず第一段階ですね。
アプローチするための5つの方法
では、実際に算定するにはどういったアプローチが必要なのかを説明していきます。
算定につながる行動としては、主に次の5つの方法が挙げられます。
普段一包化を行っている患者さんに対しての声かけ
一包化をしている患者さんは、そもそもアドヒアランス不良であったパターンが多く、一包化した後も残薬をある程度持ってしまっていることも多々あります。
そこでブラウンバッグの出番です。その貯まった残薬を一度持参してきてもらい、整理をしましょう。



いわゆるブラウンバッグ運動を店全体で行う形ですね。
チラシやポスターを作ってみてもいいでしょう。
一包化患者の併用薬を確認し、2科以上かかっている患者さんに声かけ
一包化している患者さんで、他科にもかかっている方は意外と多くいます。そもそも折角の一包化も、複数の科で分かれてしまってはアドヒアランス改善効果も半減です。より服薬管理状態を良くするためにも、一か所でまとめて分包する意義は大きいかと思います。
まとめて分包をしてくれることを知らない患者さんも多いため、積極的に提案していきましょう。
この方法の過程で、処方箋受付回数の増加、かかりつけ薬剤師制度の同意へも繋がります。
はじめて一包化を行う患者さんに声かけ
はじめて一包化を行う場合、その時点で必要性があって行うことが前提となります。なので、その日の夜や次の日の朝など、早い段階から一包化した薬を飲み始めてもらうことをおすすめしましょう。
通常はある程度の余剰薬は手持ちがあることが多いため、その時点での数日の余っている薬を次回ブラウンバッグに入れて持参してもらいます。それにより次回来局時の算定に繋がります。
ポリファーマシーであり、アドヒアランスが普段より不良の人に声かけ
これは『はじめて一包化を行う患者さんに声かけ』の発展版ですね。こちらから積極的に一包化を提案し、そのまま同じ要領で次回算定に繋げます。
一包化が叶わなくとも、整理するだけでも算定できるので、バッグは渡して次回持参してもらいましょう。直接家に回収に行くという荒業もあります。



家にたくさん貯め込んでしまっているのに、なかなか残薬調整をさせてくれない患者さんって結構いますよね。(汗)
在宅訪問開始時の残薬整理
こちらは普段より往診をする医療機関や施設との関係作りから始まります。新規の患者さんへの訪問前に、残薬を整理する役割を積極的に担います。
上手く形を組むことが出来れば、新規の患者さんとの契約のたびに安定した算定を行えるようになります。
ただ、ここで注意したいことが2点あります。
一つ目は、在宅患者訪問薬剤管理指導料や居宅療養管理指導料を算定した月には、算定できないことです。
これらの算定タイミングを敢えて遅らせて、わざわざ次の月から算定を開始する形となります。
二つ目は、2024改定にて新設された在宅移行初期管理料とは同じタイミングで取れないことです。
どちらも点数的には敢えて低い方を取る形となります。
地域支援体制加算の算定要件さえ満たせたならば、その後は敢えて外来服薬支援料1で算定するものではないでしょう。
実際の算定例を元に、算定までの流れを解説
アプローチの方法は掴めましたでしょうか?
ここまでくれば、あとは算定の流れでミスをしなければ大丈夫です。



とはいえここが一番不安なところですよね。
それでは、実際に私の担当している薬局で算定した際の流れを、いくつかの実例とともに説明していきます。
普段一包化を行っている患者さんに対しての声かけ
- 普段より一包化をしている精神科の患者さんの服薬指導中、残薬があることを確認。
ブラウンバックを渡し、次回受診時に残薬を持参するようにお願いをする。 - 次回来局時、持参された薬を整理し、再一包化。(ついでに残薬調整を行い、重複投薬・相互作用等防止加算も算定)
- その場で処方箋受付と共に、外来服薬支援料1(注2)を算定(この際、外来服薬支援料2は算定できないので注意)
- 医療機関に情報提供を作成・提出(次回、服薬情報等提供料2を算定)
一包化患者の併用薬を確認し、2科以上かかっている患者さんに声かけ
- 手帳の併用薬から整形外科の定期薬をもらっていることが確認できた、一包化希望の患者さん。
門前である内科の処方せん受付タイミングにおいて、投薬時にこちらですべてまとめることができる旨を伝えます。
そして、次回受診時に、整形外科の処方せんとともにその時点で服用中の一包化された薬を持参してもらう約束を取り付けます。 - 当日受診した整形外科の処方箋と、持参薬をまとめて預かります。この際、処方元にTELLをし、まとめての一包化の許可をもらいます。
- 預かった整形外科の処方箋の薬と、持参してもらった内科の薬をまとめて一包化してお渡しします。
- 外来服薬支援料1(注1)を算定します。
在宅訪問開始時の残薬整理
- 施設より新規入居利用者の連絡を受ける。持参薬は一つの袋にまとまっていることが多いため、そのまま保管しておいてもらいます。
- 処方医に連絡をし、一包化・再分包の服薬支援の許可を得ます。
- 持参薬を回収し、再分包等の加工・整理をし、施設の所定の場所にセットをします。
- 外来服薬支援料1(注1)を算定します。この際、同月に居宅療養管理指導料を算定してしまわないように注意しましょう。
と、このような流れで算定まで漕ぎつけることができます。
実際にやってみればわかりますが、どの流れの結果でも、とても感謝をしていただけます。



それだけ調剤後の薬剤の整理は求められているということですね。
ここまで読めば、かなり明確に算定までのイメージをつかめたのではないでしょうか。
算定が厳しい店舗条件とその対策
とはいえ、算定が厳しい店舗の条件というものも実際に存在します。
小児科・整形外科・皮膚科・婦人科・耳鼻科・眼科等から主に受け付けており、算定対象となり得る患者さんが極端に少ない薬局はそもそも機会が少ないため算定が難しいです。
さらに完全門前型で、他院からの処方せん受付が極端に少ない場合は絶望的と言っていいでしょう。



それだけ患者さんの属性に左右される算定とも言えます。
それでも、近所に住まわれている、かかりつけ薬局として来てくれている患者さんはきっと数十人はいるはずです。
そのなかにアプローチ可能な患者さんがいないか探してみましょう。
また、在宅の案件さえ掴むことができれば、その先は地域支援体制加算に関わるあらゆる算定の宝庫です。
外来服薬支援料1も例外ではありません。
あきらめずにできることを探していきましょう!
まとめ
- 地域支援の算定要件変更により、外来服薬支援料1算定の需要は高まっている。
- 算定対象としては
①ポリファーマシー患者
②日常的にアドヒアランスが不良
③普段より一包化している
④認知症が進んできている
⑤家族orヘルパーさんが薬を取りに来ている
が挙げられます。 - アプローチ方法としては
① 普段一包化を行っている人に対しての声かけ
② 一包化患者の併用薬を確認し、2科以上かかっている人に声掛け
③ はじめて一包化を行う人に声かけ
④ ポリファーマシーであり、アドヒアランスが普段より不良の人に声かけ
⑤ 在宅訪問開始時の残薬整理
が挙げられます。 - 算定が厳しい店舗は存在しますが、チャンスがないわけではありません。
かかりつけの患者さんや在宅の獲得など、可能性を模索していきましょう!
いかがでしたでしょうか?
ハードルが高いイメージであった外来服薬支援料1が、手の届く範囲に来たように感じられたのではないでしょうか?
該当の患者さんが何人も浮かんだよ、って方もたくさんいるのではないかと思います。
やってみるまでが不安で、一度やってしまえばこんなものかと思えるようなことは往々にしてあります。



なにより必要なのは恐れず面倒くさがらず、行動をすることです。
明日からと言わず、今日から早速行動してみましょう!
また、ここまで読んだ上でも外来服薬支援料の算定が難しいという人がいましたら、直接ご相談ください。
私が一緒に考えます!
ここまで読んでいただきありがとうございました。
皆様の薬剤師ライフのお役に立てると嬉しいです!
それではまた、次回の記事でお会いしましょう!
執筆者: つかさ
楽屋裏座談会



皆さんどうですか?
外来服薬支援料1は取りに行ってますか?
実際どれくらい算定できていますかね。



私のところは隣が総合病院の門前というのもありまして、もともと二科以上の診療科にかかっている患者さんがとても多い状況にあります。
なのでそもそも外来服薬支援料1を算定する機会は多かったですね。



それはすごいですね。



それとは別に担当している施設がありまして。
そこの初回入居時にも服用中の薬を整理をする機会はありますね。



ということは今回の地域支援体制加算の要件が変更になって頑張りだしたというよりも、もともと取れていたという形ですかね?



それが元々とれる状況にはあったのですが、あまり優先して取ってはなかったんですよね。
患者さんが持ってきてくれた薬をまとめた時も、その日の処方箋受付の方で外来服薬支援料2にしちゃってたり。



総合病院だと日数が長いことも多くて、その方が点数的に高いことも多いですしね。



そうなんですよね。



処方日数やその時すでに地域支援の要件を満たせているか等で優先順位が変わることはあると思います。
かいくんのところはどうですか?



担当のエリアは全店地域支援の要件を満たす程度には算定できました。



流石順調ですね。



とはいえ苦労しました。
例えば小児科はそもそも急性期ばかりでたくさんのお薬を飲むことも無いので、対象患者がすごく少なかったんですよね。



小児科で定期薬の一包化をすることなんてほとんどないでしょうしね。
ではどのようにして算定できたのですか?



基本近隣にお住まいの、内科にかかっている高齢の方への声かけですね。
あとは一人、小児の総合病院に定期的に入院するお子さんがいらっしゃって、その方の退院時処方がまたすごく複雑で。
それをまとめる作業を依頼していただきました。



それはいいタイミングでしたね。
実際外来服薬支援料1の意義に沿っているというか、お手本のような支援内容かと思いますよ。



かなり時間はかかるので、単体で利益になっているかというとちょっと微妙なところなんですけどね。(汗)



普通の一包化よりも大変そうですもんね。



あとは内科は問題ないんですけど、婦人科もやっぱり大変で。



婦人科さんもね、やっぱり一包化が少ないですし。



比較的若いですしね。



そうなんですよ。
そもそも外来服薬支援料1の支援内容に該当するような介入機会がなかなか……。むずかしいですね。



婦人科の患者さんの中でっていうとかなり厳しそうだね。
一包化が算定にマストではないとはいえ、そもそも整理するほどの薬の数がないでしょうし。



他と比べて、他科への受診も少ない傾向にあるように思います。



確かに。その疾患だけというか、本当に婦人科にしか受診していないイメージはありますもんね。



他科案件でも、軽い症状なら婦人科でそのまま出しちゃうイメージもありますね。



そうなると本当に算定機会は見つけづらいですね。



はい。それでも内服がある分、皮膚科や眼科よりはまだ難易度はちょっと低いのかなと。
頑張ればチャンスはあるのかなと思っています。



皮膚科と眼科はねぇ。
うちの担当エリアにもあるけど、内服がそもそも少ないからかなり難易度高いですね。



実際婦人科さんでは算定できたんですか?



担当施設の入居前の残薬整理で算定できました。(笑)



そういえばちょうど新しく施設始まったんだっけね。



そうなんですよ。
結局外来の患者さんからはまだ該当者は見つかっていないんですよね。



でもとりあえずは一安心ですね。



二人ともありがとう。
僕の担当のところは、苦労もありながらも大体算定することができて、耳鼻科とかの外来では厳しいところもあったけど、施設や個人宅の導入で大体なんとかなったかな。



担当店舗多いのに、流石ですね。



ただ一か所。医療モールの薬局が基本料1から2になってしまって。
元々幅広く頑張っている店舗だから、可能なら地域支援の4を取りに行きたくてね。
そのために必要な外来服薬支援料1の算定回数は、なんと年間60件以上!



60件!?



途方もないですねぇ。(汗)



とはいえ、それでも循環器科や精神科のあるモールだから、算定機会は多いね。
そもそも母数がやっぱり多いですし、施設もいくつか抱えているのは大きいですね。
今のところ月に5~7件算定できているから、来年までには要件を満たせるんじゃないかなと思っています。



すごいですね。



外来服薬支援料1は同じ人から何度も取れるものじゃないので、継続して算定していくのはかなり難しい印象です。



そうですね。特に残薬整理の場合は再度同じことが起きないように努力をすることが前提になっていますし。
でも現実として、頑張ってもなかなか改善されないことは多々ありますね。



外来服薬支援料1はどれくらいの頻度で算定してもいいんでしたっけ?



月に一回ですね。
でも同様の支援を今後必要とならないような支援をしていることが前提なので、同じ内容で複数回算定するようなことはやはり避けたいところです。



例えば2科以上かかっている患者さんで、処方箋を持ってくるたびにもう片方の科の分とまとめて分包をしているケースがあると思います。
その場合、月に一度分包の機会があるなら毎月算定し続けることができるようにも思いますが、どうなんでしょうか?



否定される根拠はないかと思います。
実際それで算定し続けているという話も聞いたことはありますね。
ただ地域によってもその内容で保険者より連絡が来たという話もあって、どこまで踏み込んでいいのかは悩みどころです。



点数的にも外来服薬支援料2を算定するのとほとんど変わらなさそうですしね。外来服薬支援料1を優先することで、むしろ低くなることもありそうです。



やることはやっていますしね。
明確にわかる人がいれば教えてほしいところです。



他になにか話したい事はありますか?



私は注1と注2ってよくごっちゃになっちゃってて。
このページを見たらすごくわかりやすくて良かったです。



それはうれしい意見ですね。
僕も最初はよくわかっていなくて、とりあえず注1っぽいし、こっちでいいかな。とか。
でも後でよく見たら注2だったかも。とかっていうのも正直ありましたよ。(笑)



そうなんですよね。
とりあえず困ったら注2にしておけばいいのかな、とか。



実際ブラウンバッグ運動を行っているところならば、注2で網羅できる部分は多いかと思います。
ただ患者宅に訪問して回収した場合は注1になるので注意が必要ですね。
施設の初期なんかでこちらから取りに行く場合もそれに当たるかと思います。



気を付けないとですね。



とはいえ点数は変わらないですし、切られた試しも今のところはないですけどね。
ただ個別指導ではやっぱりそういったところもしっかり問われるので、ちゃんと把握しておきたいところですね。



記事をみて、注1と注2の違いをやっとちゃんと理解しました。
恥ずかしながら。(笑)



わかりやすい記事になってくれていればうれしいです。



まだまだ勉強しないとですね。



私ももっと頑張らないとと感じました。



お互い頑張っていきましょう!
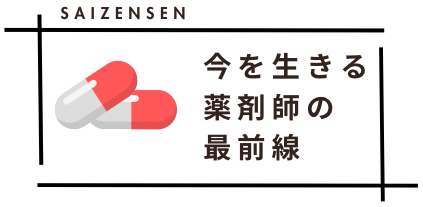
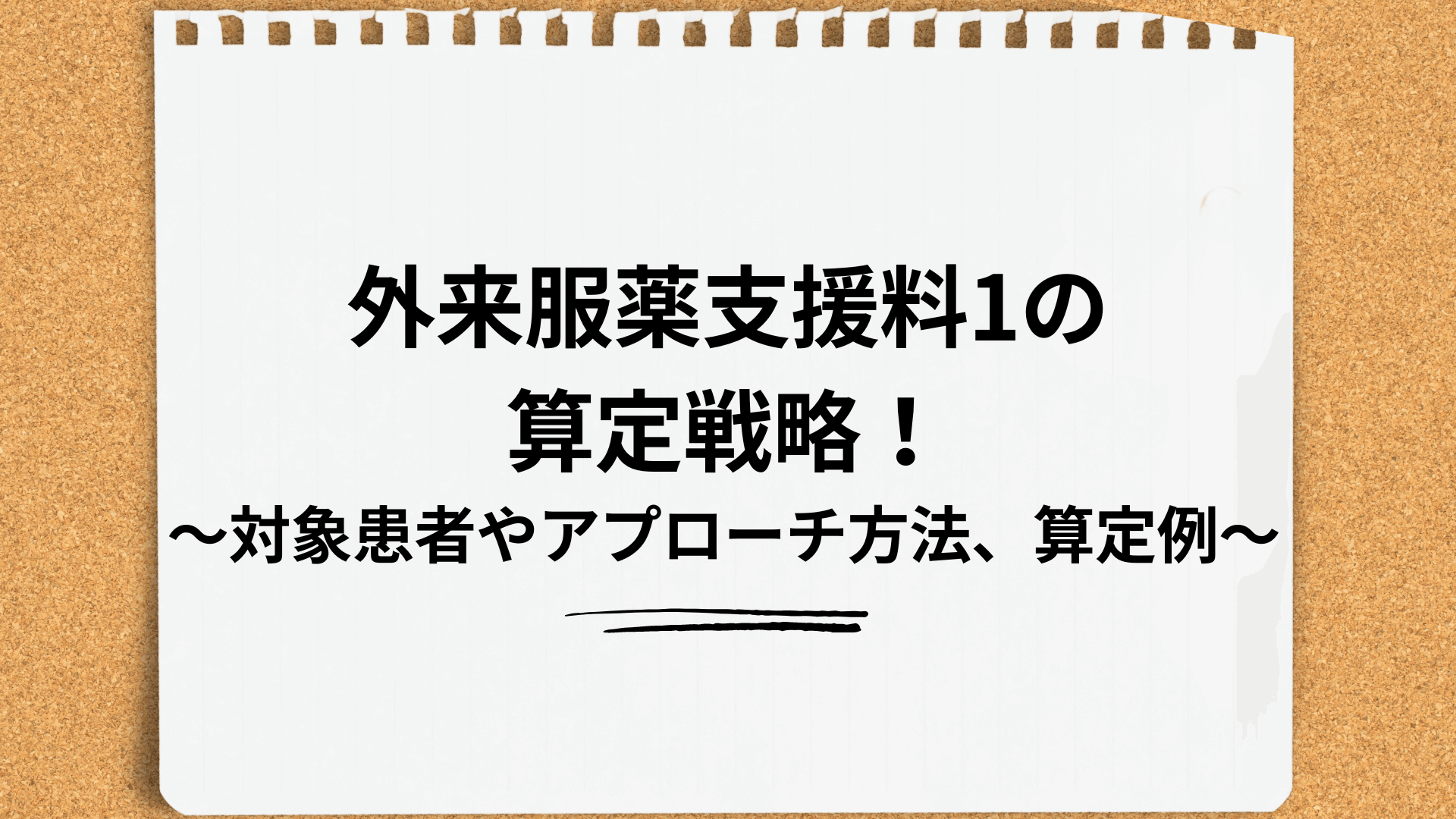
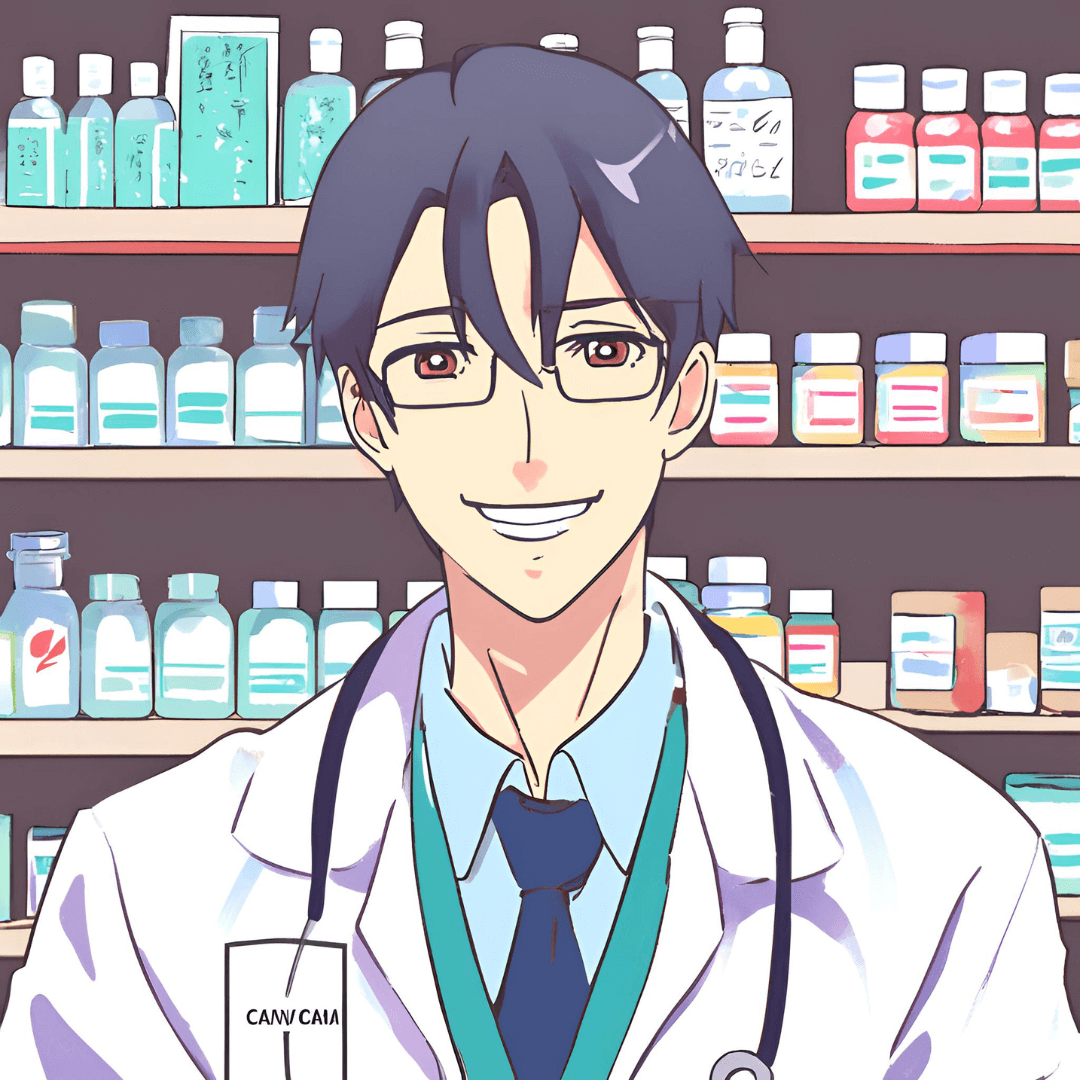
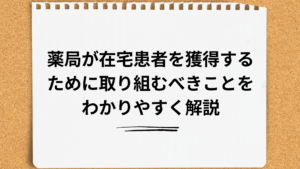
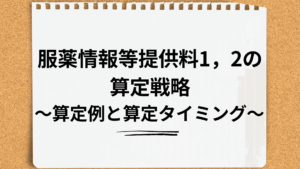
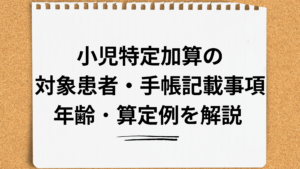
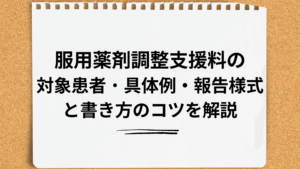
コメント